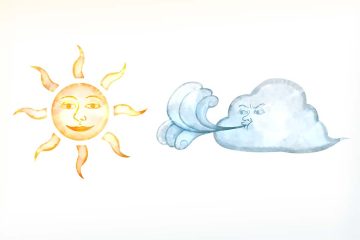小学5年生の5月
ある朝、子供が6時に起きて7時に家を出ていきました。その日の前の日は、私も一緒に起きてご飯を用意したり食べたりしていたのですが、連日の疲れが重なり、その日は寝させてもらうことに。出かけた音を聞いて起きてみたら他の家族も睡眠中。シンクにご飯茶碗と味噌汁茶碗がちょこんと置いてあり、子供が自分でご飯を温めて食べてから出かけたことに気付きました。文字通りの「お膳立て」がいるかなと思っていたら、いつのまにか1人でてきぱきこなすようになっていました。
そういえば、飼育係の当番は月・木だったはず。今日は火曜なのになぜ?と思って家族に聞いたら、◯◯ちゃんが当番だからとのこと。
◯◯ちゃんは、よく嫌がらせをしてくる同級生の名前。どういうこと?と聞いたら、◯◯ちゃんも良いところがあるから、仲良くなろうと思って、とのこと。1年前には考えられないことを考え、行動するようになっていました。
小学4年生の5月
ちょうど1年前の5月。4年生だった我が子は、不登校のような状態になっていました。
4月になり、仲の良い2人の友達が同じクラスになり、楽しい毎日を過ごせると考えていたのですが、3人だとうまくいかず、2人が仲良くなるともう1人が拗ねたり、2人が1人を仲間外れにしたりを繰り返していました。
特に、3年生の時には大親友と思っていた子から嫌いと言われた時はショックが酷く、校内でも帰り道でもひとりぼっちになってしまい、早退、不眠、そして不登校となってしまいました。
親としては気が気でなく、我が子の不安を受け止めて無理をさせないようにしつつも、このままだと永遠に学校に行かないのでは?という恐怖に駆られました。私は下の子の園バスの送迎で、片方の友達の親と毎日顔を合わせていましたので、その時に何か言おうかとも思ったのですが、そのせいでますます子供たちの関係性が悪くなるのではと思い、何も言わずにいました。
しばらく経っても学校に行く気配が一向になく、不眠も続いていたことから、何か手を打たねばと、カイロプラクティックや鍼灸に行ったり、自宅で子供にマッサージをしたりもしました。また、スクールカウンセラーや担任の先生にも相談しました。
特に、担任の先生に何を相談するかは慎重に慎重を期しました。相手の親にクレームを入れてもらう、子供たちに先生から直接注意してもらう、という案もありましたが、最終的には、きっかけのために仲介はしてもらうけれども、当人同士で話し合いをするようにしてもらう、という結論になりました。
その後、少し学校に行けるようになり、でもまた少し休み、その後にまた行けるようになり、というのを繰り返し、仲良くなったり、仲違いをしたりを繰り返しつつ、ついに今年の3月、辛かった4年生をなんとか終えることができました。
小学5年生の4月
5年生になるとクラス替えがあり、その友達の1人が別のクラスになり、もう1人が同じクラスになりました。ほどよい距離感でバランスが良くなったのですが、同じクラスになった友達との間に入ってくるのが◯◯ちゃん。我が子を遠ざけようと、悪口を言ったり、わざと仲間外れにしたり、いやはや、なかなかうまくいかないものです。
学校に行きたくない!またその言葉を聞いた時は、去年の5月の再来かと憂鬱な気持ちになったものです。
しかし、今年の5月は、冒頭に書いた通り違いました。自ら◯◯ちゃんに近づこうとしています。表に見えるわけではありませんが、避けたり、耐えたり、倒れたりしていた去年とは違い、心が叩かれても蹴られても、諦めずに立ち上がり、前に進んでいこうとしています。子供の心の中の葛藤と戦いが目に浮かぶようで、逞しくなったなあと、日々強くなる我が子を頼もしく思っています。
葛藤や立ち向かう機会を奪わないこと
いきなり「リーダーとは」という話に飛びますが、自身がリーダーをしていて、メンバーが苦労をしていると、どうしても助けたくなりますし、巻き取りたくもなります。
とりわけ、時間がない時だと、本人が考えたり動いたりする時間が惜しくなり、早く終わらせることを優先して自分でばしっと終わらせてしまいたくもなります。
本人のスキル的に無理がある時や、本当に緊急の時は、そうするのもやむを得ないでしょう。先のエピソードで言えば、相手の親に直接話し、担任の先生に子供たちに直接注意して貰うのも、あまりに酷い場合は必要でしょう。
でも、仮にあのときそれをしていたら、この小学5年の5月はなかったかもしれません。
辛い気持ちや苦しい気持ち、もどかしい気持ちはどうしても生まれますが、焦ることなくじっくり待つことも、成長のためには必要なことと実感したある日の出来事でした。